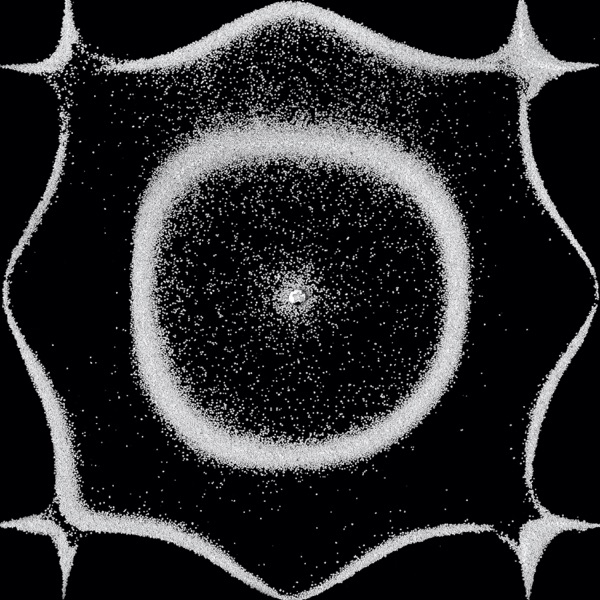やる気こそ感じられないがしっかりとリズムに対するフロウがあり、「Some Rap Songs」に較べると余程ちゃんとラップしていると言える。
トラックにはやはりこれと言ったフックは無く相変わらずデプレッシヴで空疎ではあるが、前作にあったような極端にアブストラクトなものは少ない。
Madlibに通じるようなクラックル・ノイズ塗れのサンプリング・ループ・ベースのプロダクションや珍妙なSE、ダビーなエフェクトは健在だが、何時になくビートは明瞭で破綻無く安定している。
得も言われぬフリークネスや異物感は薄まった印象で、「I Don't Like Shit, I Don't Go Outside」以降で最の普通のヒップホップ/ラップ・アルバムに聴こえる。
前作と違うのはEarl Sweatshirt自身の手によるトラックがほぼ無い点で、代わりに3曲をThe Alchemistが手掛けているのが比較的オーソドックスな印象に拍車を掛けているのかも知れない。
確かにFreddie Gibbs & The Alchemist「Alfredo」にも近い燻銀的な、少し悪い言い方をすれば地味な印象で、決して悪くはないが期待値が高かっただけに少し物足りない。
収録時間も前作同様に短く(24分しかない)、然した引っ掛かりも無いままに何時の間にか終わっている印象で、肩透かしを喰らった感は否めない。
確かに「Some Rap Songs」よりもずっと聴き易くはあるが、異端児であり革命児でもあるEarl Sweatshirtにそんな事は期待していないのだ。